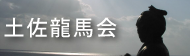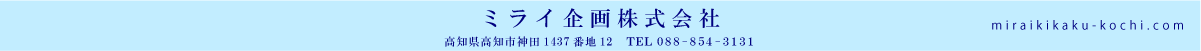ごあいさつ
はじめに
私、田村 滋は長年農業土木の仕事に関わり、中四国農業土木学会に実験や研究の発表を行ってきました。
令和元年の節目の年に、これまでの50年間、蓄えてきた、県下の農業農村整備の役割や整備、農村文化・生活・景観についての関係資料を、わかりやすく事例等をふまえ紹介いたします。
1. 農業土木学会中国四国支部発表の紹介
- 路床工…ファゴットによる処理工法について(愛媛大学)
- 新居地区(約146ha)の畑地かんがいについて(岡山大学)
- 防災水利計画にういて(調整池・排水機口径800m/m×12台)について(高知県) (高知競馬場新設工事)
- 水耕生物による農業集落排水の高度水処理について(広島大学) (春野ピオパーク)
詳しくはこちら→農業土木学会発表
2. 水耕生物による農業集落排水の高度処理
水域の富栄養化現象を改善する試みは各地で進められているが、その主流は窒素、リンを効率よく削減する方法を確立することである。特に集落排水処理施設は地域の環境保全の欠かせない施設であり、その設置が各地で進められている。しかし、その多くは沈殿物の処理やBOD削減をはかる、いわゆる一次処理または二次処理の段階にとどまり、窒素、リンの削減を含む高度処理ができていないのが実状である。
水耕植物による水質浄化方法が注目され、各地で試みられているが、この方法による浄化は、地域の気候風土に適した植物の選択と、処理を必要とする水量と水質に適合するなど、処理効率の高い施設構成であることが求められる。
高知県春野町諸木に設置された農業集落排水処理施設、春野町諸木クリーンセンターの排水をモデルとして、この種の浄化施設に関する高度処理法を確立するパイロットプラントを目指して調査研究を行った。その結果、予想外に植物の成果は早く性質の異なる植物の混植による効果的な水処理方法を確立し、水質検査の結果も計画除去率を上回る好成績をあげたのでその結果について紹介する。
詳しくはこちら→農業土木学会発表
3. 河川環境を保全しながら水資源開発は可能か
一級河川環境を保全しながら水源開発は可能か。近年ダムの建設で、河川環境や生態系を変化させることが、大きな問題となっている。
国民の多くは、防災ダムの必要性、利水上の利便性は、十分に理解しながらも、より良い環境保全が維持できることも望んでいる。 多くの河川では、河川改修が進み、洪水流下能力を向上するための努力が進められている。また、流域では、林地、農地の荒廃、都市化の進行により、降雨の河川流入形態が変化し、国土における涵養能力の低下により、河川流入水量の増大、ピーク流量の短時間発生と、ピーク流量の増大が治水上の大きな問題となっている。
また、その反面、河川による洪水流下能力の向上、利水施設の増加により無降雨時の河川流量の低下が著しく、高水時と低水時の比がどんどん大きくなり、渇水状況が長時間に亘って発生している。渇水時には、水道、工業用水不足が大きくクローズアップされるが、自然維持流量も大きな問題が発生している。
これは、平野部等での農業用水の地下水利用などで、ほとんど河川に水が無い状態が見られる。
このような、洪水時と平水時の問題を処理する方法として、今までは、ダムを建設し、洪水流量の貯水、渇水時の放流を人為的に操作し、この問題を処理してきた。
提案した洪水備蓄トンネルは、洪水調整や河川維持管理用水確保、農業用水利用等、多目的利用を目的とした洪水備蓄トンネルを紹介する。
詳しくはこちら→農業土木学会発表
4. ハ田堰改修工事について
ハ田堰改修工事につて、(1648年野中兼山工事着手・かんがい面積1.253ha・用水路延長21.989m)平成10年度の改修工事着手以来、6年間でゲート設備、管理所、護床工と整備してきたが、八田堰のような改修事業の場合には既に数十年の実績があることから、当初設計の思想を理解した上で、現在までの被災状況を分析し、その結果に加えて管理者の意見も十分反映する必要がある。
また、堰体の補強工法や護床工の規模については対象河川によって大きく異なるので、河川流況を十分認識し、各種文献や類似地区の事例等を参考にして決定する必要がある。いずれにしても河川構造物は自然を相手にするものであり、河況は一洪水で一変することも珍しくないことから今後の為に工事記録を将来に残したい。
詳しくはこちら→農業土木学会発表
5. チェックリスト「シート・審査票」作成

農業土木技術者の役割は、地域社会のニーズに応じた【技術力】の提供にあり。このため、常に技術力向上のための努力・研鑽を行うことが重要だ。
ところで近年の事業執行体制で、技術者の技術力低下がよく話題になっている。この原因は数学や物理学等の基礎学力の低下、応用化学分野の体系的な学力不足が考えられる。そして実務面では、もっぱらコンピュータによる既成プログラムを利用する作業が多く、手計算を行わない為、技術者が現地調査を充分に把握が出来ないまま設計に入り入札結果後現地と設計図面が合わない事例がある。私たちの時代は先輩技術者と同伴して現地で指導を受けた。また、現場主義で現地調査を十分に検討した上で設計業務に入ったものである。
このため、技術者育成の一環として委託・成果品の照査・審査にポイントを置いたチェックリスト「シート・審査票」を作成した。 目的は技術水準のレベルアップにあるが、初歩的な設計ミスを防ぐとともに、安全且つ、効率的・経済的に実施し技術者の設計施工に対する知識と経験による事が大切である。その為に審査票を活用して更にパワーアップした設計が望まれる。
詳しくはこちら→委託・設計の審査表
6. 防蛾灯(青色LED光源)の実験
高知県で初めて防蛾灯(青色LED光源)の現地実験を実施することができた。四万十町のショウガ、ブルーベリー農家を始め、なす、ミョウガ、大葉、オクラの生産農家で協力していただいた、県下で、防蛾灯実験を実施した結果、消毒回数を減らす効果が期待出来た。
また、消費者目線で譲れない農産物の安心、安全、また消費電力が少ないLEDは、電気代に悩む電照栽培の農家には関心が高いし、農業の生産向上につながる可能性が極めて高い青色LED防蛾灯に今後も期待したい。
詳しくはこちら→その他の研究・実験
以上実験や研究資料のまとめでございます。
今回このまとめができましたのは、関係各位のご理解とご協力のおかげです。心からお礼申し上げます。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
令和元年7月1日
ミライ企画株式会社
代表取締役社長 田村 滋